
会社の業績によって任意に支給される賞与が決定賞与です。本記事では、支給される時期や会社側のメリット、注意点について見ていきましょう。また、支給するときに天引きする税金や社会保険料についても解説します。
決算賞与とは?
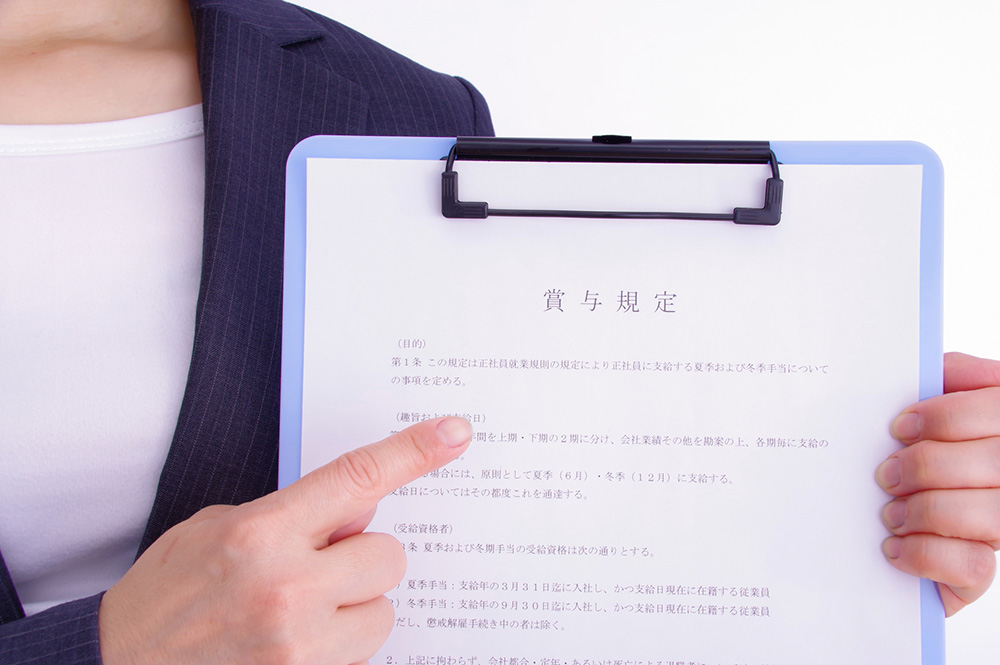
決算賞与とは、会社の業績によって支給する臨時ボーナスのことです。一般的には会社の業績が伸び、社員に還元する利益が多いときに実施します。
しかし、業績が良くても会社側に支払いの義務はないため、決算賞与を支給しないという選択をすることも可能です。
また、通常の賞与は社員個人の成績を反映して金額を決めることがありますが、決算賞与では成績を反映するケースはあまりありません。
支給時期は決算前後が一般的
決算賞与の支給時期は、決算の前後が一般的です。決算賞与として支給された金額は損金に計上できるため、予想以上に利益が多く、決算前に税金対策をしたいときなどにも実施します。
支給を通知した時点で損金算入が可能
決算賞与は節税を目的として決算期前に急に支給を決定することがあります。しかし、期末は何かと慌ただしく、支給しないまま事業年度が終了することがあるかもしれません。そのような場合でも、次の3つの条件を満たしているときは今期の損金として算入できます。
- 事業年度が終了するまでに、決算賞与で支給する額を支給対象の全従業員に対して通知していること
- 通知した金額を、事業年度が終了した日の翌日から1ヶ月以内に全額支払うこと
- 通知した金額を、事業年度が終了する前に損金計上の手続きをしていること
ただし、上記の条件をすべて満たしているときでも、以下のいずれかに該当するときは、翌事業年度に損金計上することになります。
- 通知はしたものの、既定の期間内に決算賞与を受け取れない人が1人以上存在する
- 決算賞与の支給対象者を在職者のみと規定している場合
- 通知した金額と異なる金額を決算賞与として支給した
参考:国税庁「No.5350 使用人賞与の損金算入時期」
支給対象を自由に決められる
決算賞与は、会社側が自由に支給できる賞与です。そのため、支給対象も自由に決めることができます。例えば、正社員だけでなくパートやアルバイトに支給することや、役員へ支給することも可能です。
また、決算賞与の支給は、全社員に向けて告知する必要はありません。支給対象者個々に支給額を通知することができるため、一律の金額を支給するのではなく、役職や会社への貢献度を加味して金額を決めることができます。
決算賞与を支給する会社側のメリット

決算賞与を支払うことには、さまざまなメリットがあります。社員にとっては収入が増える点がメリットになり、会社にとっても下記のようなメリットがあります。
- 社員のモチベーションアップ
- 法人税などの節税につながる
それぞれのメリットについて解説します。
社員のモチベーションアップ
決算賞与は、通常、予定よりも利益が多かったときに実施します。つまり、社員にとっては成果が出ると賞与をもらえることになるため、仕事に対するモチベーションアップにつながります。
また、決算賞与に会社への貢献度が加味されている場合、個人の努力が報われる形になるためより一層強く従業員をモチベートすることができます。
しかし、決算賞与が社員のモチベーションを下げる原因になることもあるので注意が必要です。
例えば、業績が右肩上がりで毎年決算賞与を支給していた場合、社員にとっては決算賞与を受け取ることが当然になってしまい、支給されないときには不満を感じる可能性があります。
決算賞与がモチベーション低下の要因とならないよう、支給基準を明確にしておくと良いでしょう。
例えば、増益と決算賞与の関係を明記したり、売上目標に到達したときに一律で決算賞与を支給したりすることで、決算賞与をモチベーションアップにつなげやすくなります。
法人税などの節税につながる
決算期末が終了する前に決算賞与の支給を決定し、対象となる従業員に通知をすると、今期中に損金計上することが可能です。損金が増えると課税対象額を減らせるため、法人税などを節約できます。
決算賞与を支給する際の注意点
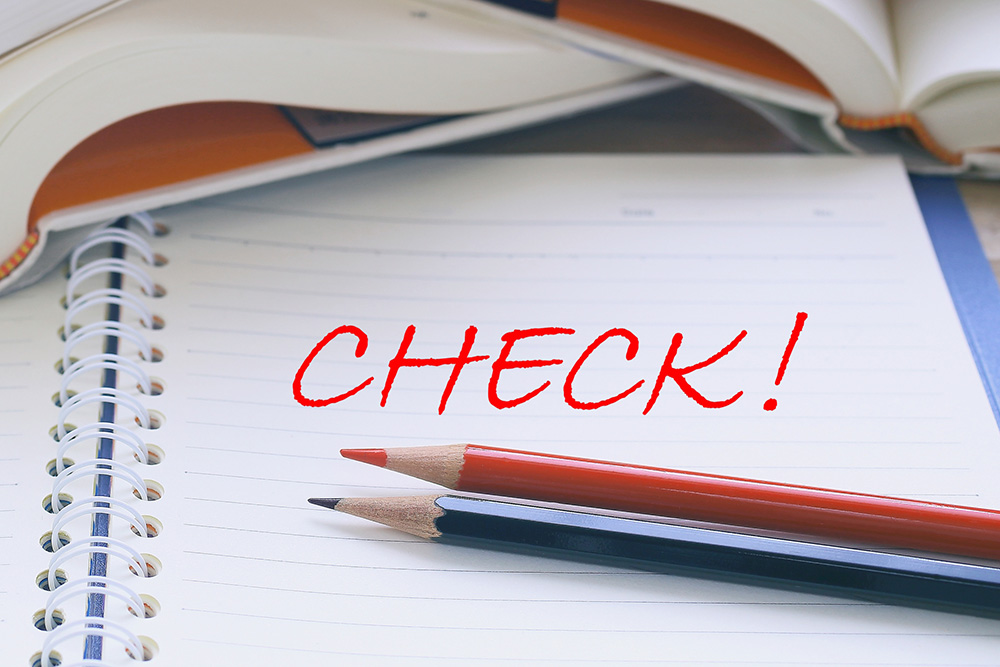
決算賞与には注意点もあります。企業側が注意すべきポイントとしては、次の6点が挙げられます。
- 手元資金が減る
- 損金算入した決算期末から1ヶ月以内に支給する
- 役員の決算賞与は損金算入できない
- 通知後に退職した社員へも支給する
- 損金算入できるのは通知額まで
- 社会保険料の損金算入は賞与支給の時期と同じ
それぞれのポイントを解説します。
手元資金が減る
決算賞与は、余剰金ではなく収益の一部です。当然ですが、支払うと会社の手元資金が減る点に注意しましょう。
例えば、支払い期限が迫った買掛金があるとき、設備投資が必要なときなどは、利益が予想以上にあっても全額を決算賞与にすることにはリスクを伴います。資金計画を綿密に立て、支給した場合の社員のモチベーションアップも検討した上で金額を決めましょう。
損金算入した決算期末から1ヶ月以内に支給する
決算賞与支給額を今期の損金として計上した場合は、事業年度が終了した翌日から1ヶ月以内に社員に支給しなくてはいけません。
損金扱いにしたものの、手元資金が少ないために1ヶ月以内の支給が難しいときは、翌期の損金として計上するほうが良いでしょう。また、支給してから資金繰りが厳しくならないように、十分な手元資金を残しておくことも重要です。
役員の決算賞与は損金算入できない
決算賞与は、会社が自由に支給対象者を決めることができる賞与です。そのため、従業員だけでなく役員にも決算賞与を支給できます。しかし、原則として役員の決算賞与は損金算入できない点に注意しましょう。
通知後に退職した社員へも支給する
決算賞与を支給すると通知した対象者に関しては、対象者が離職した場合であっても支給しなくてはいけません。定年退職した場合や転職した場合も忘れずに支給しましょう。
ただし、損金算入する事業年度に勤務していた場合でも、支給対象者と定めていない場合は支給する必要はありません。漏れなく支給するように、支給対象者と支給額を確認しておきましょう。
損金算入できるのは通知額まで
決算賞与は、あらかじめ通知した金額を対象者に支給する形の賞与です。支給額を決めた後に多額の利益が生じ、決算賞与の金額を増やす場合には、通知額までしか損金算入できません。
節税効果を高めることを目的とするのであれば、通知した金額を正確に支給しましょう。
社会保険料の損金算入は賞与支給の時期と同じ
決算賞与自体は、事業年度が終了するまでに支給対象者に通知していれば、今期の損金扱いにできます。しかし、決算賞与にかかる社会保険料に関しては、決算賞与を支払ったタイミングによって損金算入の時期が決まる点に注意しましょう。
年度終了までに決算賞与の通知をし、翌事業年度に支給した場合は、翌期の損金扱いになります。今期の損金として支給したいときは、早めに支給しましょう。
決算賞与の計算方法

決算賞与は、給与と同じく税金と社会保険料を控除してから支給します。それぞれの計算方法について見ていきましょう。
税金
決算賞与から差し引く税金は、所得税と復興特別所得税のみです。住民税に関しては決算賞与や通常の給与などをすべて合計した所得から計算して、翌年の6月から翌々年の5月までの給与から分割して差し引くため、決算賞与の支給時には考慮する必要はありません。
所得税額と復興特別所得税額に関しては、以下の計算式で求めます。
所得税額=(決算賞与額-社会保険料)×賞与に対する源泉徴収税率
復興特別所得税額=所得税額×2.1%
参考:国税庁「決算賞与金の税務上の取扱いについて」
社会保険料
決算賞与から差し引く社会保険料には、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料があります。賞与対象者が40歳以上の場合には、介護保険料も計算し、差し引くことが必要です。それぞれの保険料は、以下の計算式で求めます。
健康保険料=賞与支給額×健康保険料率×1/2
厚生年金保険料=賞与支給額×厚生年金保険料率×1/2
雇用保険料=賞与支給額×雇用保険料率(労働者負担分)
介護保険料=賞与支給額×介護保険料率×1/2
なお、上記の計算式において、賞与支給額は1,000円未満を切り捨てて適用します。
決算賞与の計算を正確に行おう

決算賞与を今期の損金扱いにする場合は、早めに計算し、早めに支給することが求められます。しかし、決算賞与自体、決算期末が迫った状態で実施することが多く、場合によっては翌決算期に損金計上することにもなりかねません。
通常の給与と同じく税金や社会保険料を控除した状態で支給するため、計算の手間もかかります。
MASONの給与計算アウトソーシングでは、決算賞与の計算にも対応しております。アウトソーシングサービスを活用し、決算期の忙しさを軽減してみませんか。詳細なサービスのご紹介やお見積り依頼など随時承っております。
ぜひお気軽にご相談くださいませ。
